前提と含意
前回、全体をまとめ上げる役目を果たす文(センテンス)が文章(テキスト)の構成要素のなかに存在することを示し、その最も有効な例として名詞述語文の仕組みを提示しました。
ひとつのセンテンスだけに収まることなく、連文情報をつなぎあわせ、テキスト全体にまで影響を与えることの出来る表現には他にどのようなものがあるのか、今回も紐解いていきたいと思います。
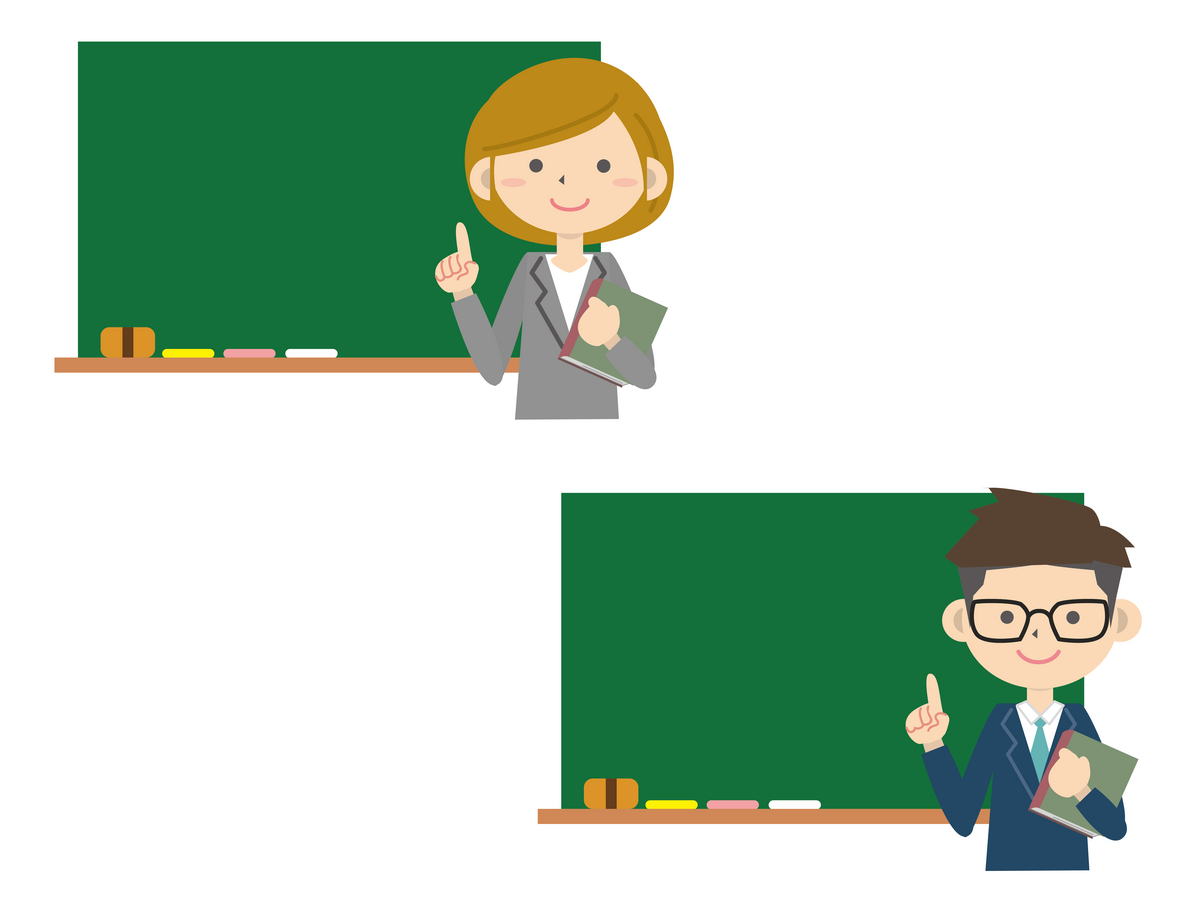
まず、真っ先に思い浮かぶのは、「とりたて助詞」による主張提示の表現です。
「とりたて助詞」とは、それを含む文で述べられている命題内容(前提)と、それに対する話し手の捉え方(含意)を同時に表す、「は」「も」「さえ」「しか」「だけ」といった副助詞のことを示します。
たとえば、
「森本先生しか、味方になってくれなかった。」という文の場合、
Ⓐ『前提』森本先生が味方になってくれた(こと)
といった事実(命題)があくまで前提にあって、さらに、
Ⓑ『含意』森本先生以外は味方になってくれなかった(こと)
というように、「森本先生以外の人」は味方になってくれなかったことを暗示しているんですね。こうした暗示的な意味を「含意」といいます。
このように、文中の要素についてその要素やその要素が表す出来事などに対する書き手の気持ちを「含意」として暗示することを取り立てるといい、そのことを表す助詞は「とりたて助詞」と呼ばれているんです。
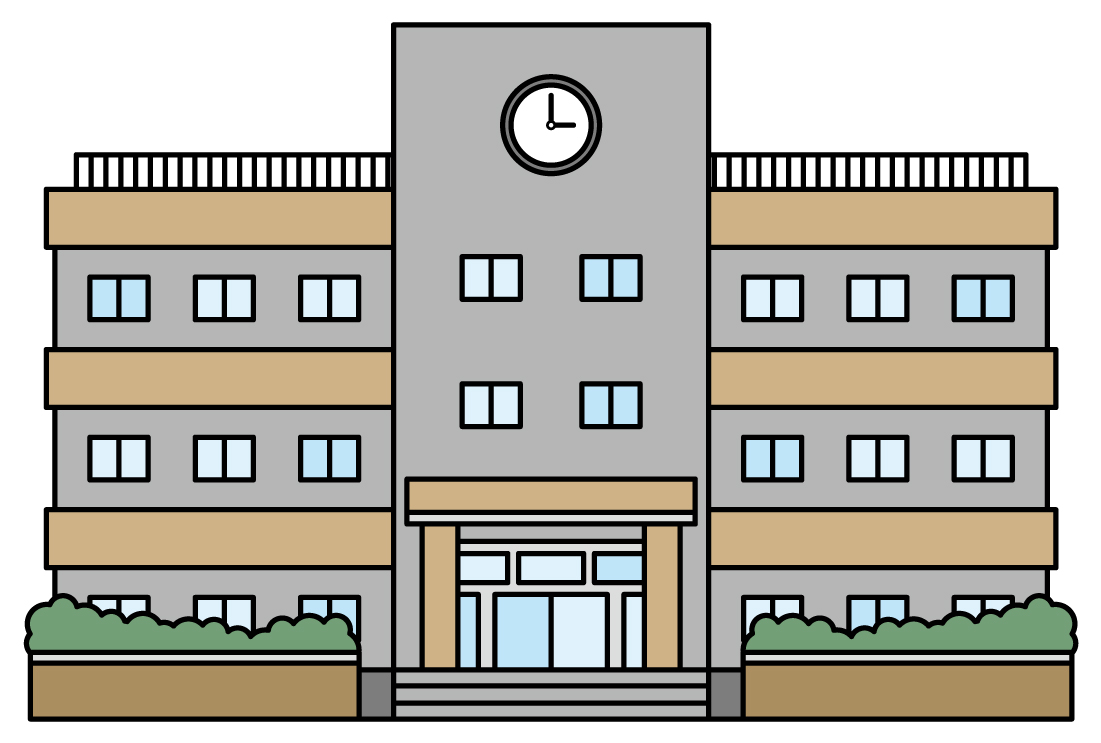
ここで最も大切なことは、この、「森本先生しか、味方になってくれなかった。」という文のなかの「しか」というとりたて助詞は、下記の例文に見られるように、取り立てている「森本先生」以外のものを連想させる機能を持っているということです。
Ⓒ森本先生だけは、味方になってくれた。
Ⓓ他の先生たちは、誰一人として信じてくれなかった。
Ⓔクラスメートたちはもちろん、用務員のおじさん、給食係のあばさん達にまで無視された。
「森本先生(しか)」という助詞によって、上のⒸⒹⒺの例文のように、「味方になってくれなかった」他の先生やクラスメート、職員の存在が連想させられるんですね。
もちろん、ⒸⒹⒺのセンテンスは文脈としてテキスト内に明示されていないこともありえます。
ですが、そのような場合でも、「しか」というたったひとつの助詞だけで、読み手に対して、このように強く潜在的に暗示させることは充分に可能なわけなんです。
おそらく、とりたて助詞がテキスト全体に及ぼす影響というのは、これほどまでに大きなものなのでしょう。
これが、「が」「を」「に」「から」といった名詞と述語をつなぐ役割を担う「格助詞」だとこうはいきません。
用務員のおじさんが何かを察したように、朝早くから、正門を開けていてくれたのだ。
という例文から見てもわかるように、用務員のおじさん「が」、正門「を」という格助詞は、あくまで「開けていてくれたのだ」という述語に係っていくだけの役目だけしか果たせないんです。
用務員のおじさんが、開けていてくれたのだ。
何かを察したように、開けていてくれたのだ。
朝早くから、開けていてくれたのだ。
正門を、開けていてくれたのだ。
そう、たったひとつのセンテンス内でその役目を終えてしまうのです。格助詞たちは、テキスト全体に影響を及ぼすことはできません。
広がる連想
今、この記事を書いていてふと思ったのですが、逆に捉えてみると、「しか」「さえ」「だけ」といったとりたて助詞というのは、書き手の立場からすればけっこう魔法の言葉なのかもしれません。
最初の「森本先生しか」という例文を書いたあと、続く例文がスラスラと思い浮かんできて、たしかに連想が広がっていくんです。
とりたて助詞を使って書き綴っていくうちに連想はどこまでも広がっていき、潜在的な思考が自然に浮かび上がってくる、まるで、そんな機能を持って、書き手の筆を走らせてくれているかのようなんですね。

そして、「しか~ない」というとりたて助詞を、仮に含意の「否定表現」だとするなら、対比するものとして、「肯定表現」の「も」をあげることができます。
例として、ついに、校長先生も様子を見にやってきた。という文の場合だと、
Ⓕ校長先生が様子を見にやってきた(こと)が前提となり、
Ⓖ校長先生以外の人が様子を見にやってきた(こと)が含意となって、すでに「校長先生以外の人」が他にもやってきていたんだということを書き手が暗示しているのを読み取ることができるんです。
そう、「しか」と同様に、「も」というとりたて助詞は、「様子を見にやってきた」という条件を満たすために「校長先生」以外の人を連想させる機能を持っているんですね。
Ⓗ学年主任の中山先生が森本先生の言葉が気になったのか、ここを訪ねてきた。
Ⓘだんまりも決め込む教頭先生がついに動き出したようだ。
とりたて助詞を使うことで、連想の世界はどこまでも広がります。まるで「ひらめき」を与えてくれるかのように。
記事を書くときにあえて意識しないと、意外と、「は」以外の取り立て助詞を、私たちはあまり使うこともないのかもしれません。