主語廃止論
日本語の基本的な関係は「主語―述語」ではなく、「主題―解説」であるという考え方。
それは、日本の文法研究の発展に伴い、多くの学者たちに支持されるようになりました。
その理論を広く世に知らしめた存在が、高校の数学教師から国語学会へと転じてきたという、三上章さん(1903~1971)という文法学者です。
独創的な見解で知られる三上さんは、自分の意見に異を唱える者には公開の場で徹底的に議論を挑むなど、妥協を許さない性格でした。
そのために、当時の国語学会の権威者たちからは完全に異端児扱いされていたそうなんです。
ですが一方で、若手・中堅の研究者たちからは熱烈な支持を受け、時代の流れに沿うようにして、三上理論を引き継ぐ者たちは急速に増えていったんですね。
三上さんの名を一躍広めることとなったのが、1960年に発刊されベストセラーとなった、この【象は鼻が長い】という一冊です。
日本語の開眼とも例えられるその著書のなかで、三上さんが最も強く主張されているのが「主語廃止論」という理論になります。
そう、「主語」という言葉を日本語から完全に抹殺すべきであると、強く訴えてられているのです。
欧米語に見られる「主語」というのは日本語には存在しないので、「そんな言葉、いらないじゃないか」とおっしゃってるわけなんですね。
つまりどういうことかというと、たとえば英文法では、主語がはっきりしないと述語を決めることができないので、主語は述語動詞を決める重要な成分となっているのですが、日本語には、述語動詞を決める主語なるものはどこにも存在しないのです。
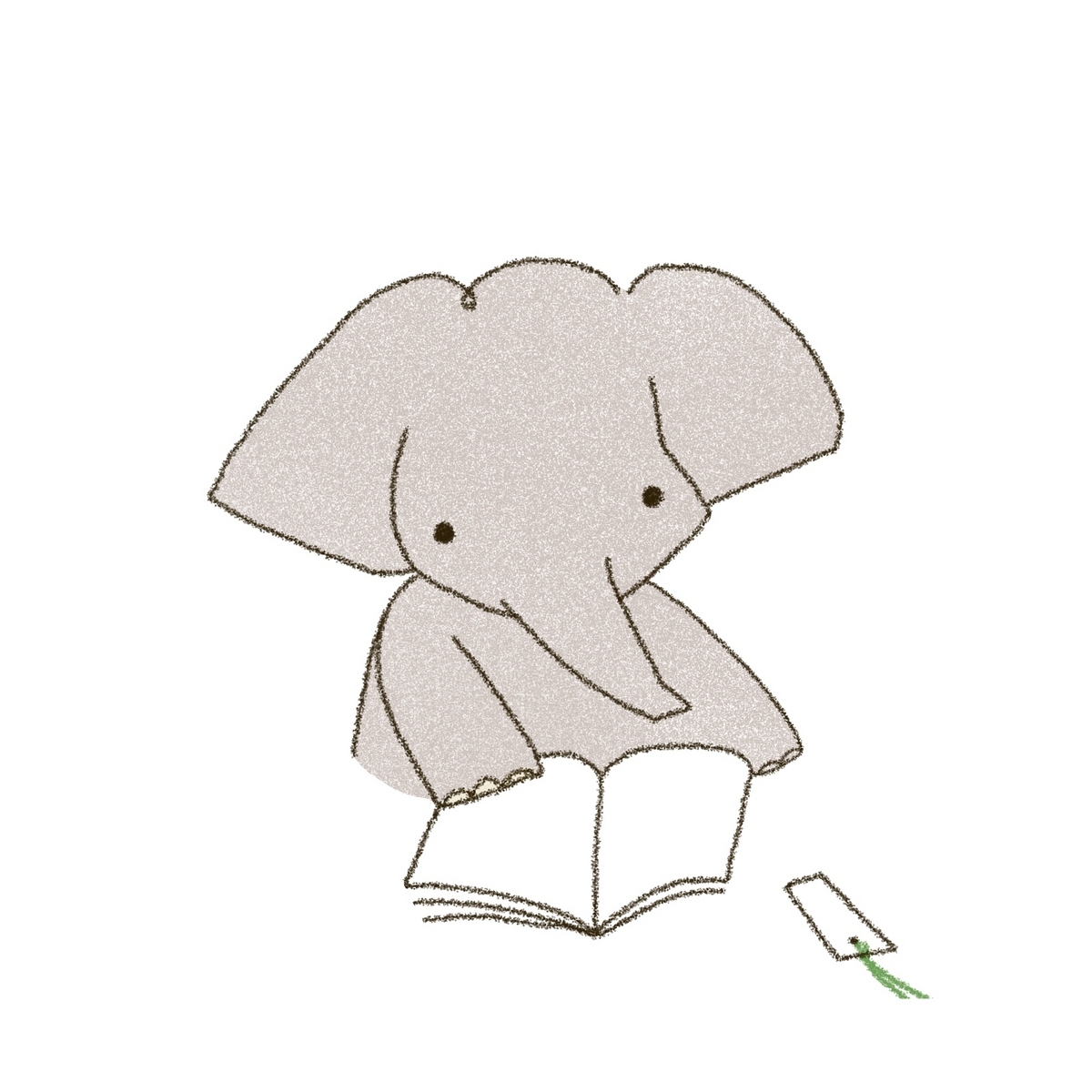
英語文では『主語+述語』という大枠があり、述語には『動詞+目的語』という枠がある、というように構造が堅固に確立しています。
まず主語が決まらないと、いっさい前には進みません。主語を立て、それを中心に客観的な陳述を続けて構成させていくのです。
それに対して日本語の文は、述語(だけ)を中心とし、事柄に応じて、構成素が述語の補語(が・に・を などの格助詞を伴う)として加わることで、いろんな文が出来るという柔軟な構造になっています。
欧米圏のように「私が」「それが」「なにが」と、一回一回、いちいち何度も主張しないし、繰り返さないのです。
この国では、状況からそれとわかるものに対しては、出来るだけ省略しようとする気持ちが働くんですね。
そんな風に、発話の場面や脈絡に依存することが大きく、主語が表出されていない独立性に欠ける表現というのが、日本語の本来の表現に違いありません。
そう、日本語文は、あくまでも「述語」が主役です。学校文法で「主語」と呼ばれているものは、その補語の一つとして付随する(ガ格成分)に過ぎないのです。
だから、「主語」ではなく「主格」と呼べと三上さんは主張されているのでしょう。
「主格」を「主語」と呼ぶと、英語の主語を想像するため紛らわしいので、あくまで構成素の一つにしか過ぎない「主格」で統一したほうがいいというわけなんです。
有題文と無題文
日本語のセンテンスは、「Xは」に注目することで、有題文と無題文に分けることができます。
「Xは」を伴い(主題―解説)という構造を持つのが有題文であり、ないのが無題文です。
例えば、
無題文 きのう佐藤が金閣寺へ行った。
有題文 きのうは、佐藤が金閣寺に行った。
佐藤は、きのう金閣寺に行った。
金閣寺へは、きのう佐藤が言った。
というように、無題文の中にあるフレーズからひとつを書き手が取り出して、「は」をつけて題にすることを提題と言います。
無題文の中からどれを取り出して題にするのかは、まさに、書き手の意思によってなされるのですから、その有題文に最も強い主張が含まれていることになります。
だからこそ、(主題―解説)で表現される有題文こそが日本語の基幹文であると考えられているのですが、一方で、逆に言うと、題「Xは」の陰には主に「が・に・の・を」という格助詞が潜在しているのも、また事実なんですね。

例文をあげると、下記のセンテンスの中身(事柄、コト)は右に続くように書き表されます。
象は、鼻が長い。
→ 象(の)鼻が長いコト
彼は、この指輪を買ってくれました。
→ 彼(が)この指輪を買ってくれたコト
日本は、空き家が多い。
→ 日本(に)空き家が多いコト
この指輪は、彼が買ってくれました。
→ この指輪(を)彼が買ってくれたコト
このように、それぞれの「は」を消して、上記のようなコトどもを取り出し代行させることをセンテンスの無題化と呼びます。
そして「Xは」には、「Xが」を代行するものが圧倒的に多いために、学校文法では「は」と「が」が主語という名のもとに、いっしょくたにされてしまったそうなんです。
キリンの首は、長い。
→ キリンの首が長くあるコト
太郎は次郎に花子を紹介しました。
→ 太郎が次郎に花子を紹介したコト
ですが、先に紹介したように、「Xは」は「Xが」だけでなく、「Xを」「Xに」「Xの」なども代行します。
だから、「Xが」以外の代行が少数だからといって、不当に軽視されるのは許されないのでしょう。
主役の「述語」に対する「が」「に」「の」「を」の役割は、あくまで対等で平等であり、それぞれが「は」とは顕在と潜在という関係にあります。
「が」を「は」と一括りにして、「に」「の」「を」たちと対極に置くなどという構文的役割の振り分けは、もはや文法と呼べないのだと三上さんは言っているのです。

「Xは」の代行となる「Xが」と「Xを」という二つの兼務。その間を揺れている表現というのも存在しますが、その場合はどちらを代行していると解釈しても問題ありません。
ロックは、あまり聞きたくない。
→ ロック(を)あまり聞きたくないコト
ロック(が)あまり聞きたくないコト
数学は、どうしても好きになれない。
→どうしても数学(を)好きになれないコト
どうしても数学(が)好きになれないコト
このように、すべての「Xは、ドウコウダ」というのは、話し手の自問自答にほかならず、「Xは」といった瞬間に何を代行するか決まってなくても大丈夫なんです。
そう、その最初の発話は、自問自答の自問すなわち題を提示しているに過ぎないのです。
そして、「ロックは」「数学は」という自問は、「聞きたくない」「好きになれない」という自答と首尾呼応していくことで、一文を完成させます。
自問の切り出しは自答の言い切りを求めてやまず、そのために「Xは」は、大きく文末に達するんですね。
たとえば、
「その計画は、もう一度考えてみる必要がある」という文の場合、
「は」の本務として、「その計画は」は「ある」と呼応するのですが、両者間に(意味上の)直接的つながりはありません。
(意味上の)関与は、「は」の兼務「その計画を」がやや小さく「考えてみ」に係って、それで終わりです。
このように「は」は文末まで大きく係り、「を」は小さくしか係ることができません。本務と兼務では射程が異なるのです。

さらに、この「Xは」の勢いは文末に達するだけでなく、ピリオドまでも越えていきます。つまり、文という枠を超えるんですね。
三上さんはわかりやすい例として、夏目漱石の「吾輩は猫である」の冒頭を引用されています。
吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。
何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いて居た事丈は記憶して居る。
冒頭の主題「吾輩は」が、「名前はまだ無い」以下の3文にまたがることで、ピリオドを3回に渡って越えていきます。
吾輩は
→ 猫である。
→ 名前はまだ無い。
→ どこで生れたか頓と見当がつかぬ。
→ 何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いて居た事丈は記憶して居る。
このような例文を見ることで、「は」という係助詞は、格助詞とは遥かに違うレベルで考察しなければならないことが実感できます。
なにしろ、その働きは文を飛び越えて、段落レベル、テキストレベルまでに及んでいくのですから。
